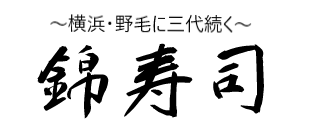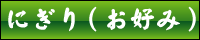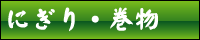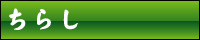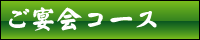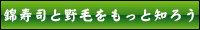寿司用語辞典
お寿司屋さん独特の言葉や専門用語を集めてみました。■あがり
 お茶のこと。もとは花柳界から来た言葉で「最後のもの」という意味があります。
すごろくのゴールや演芸での最後のお囃子が同じように「あがり」と呼ばれていて、
多くのお店では粉茶や番茶が出されます。
お茶のこと。もとは花柳界から来た言葉で「最後のもの」という意味があります。
すごろくのゴールや演芸での最後のお囃子が同じように「あがり」と呼ばれていて、
多くのお店では粉茶や番茶が出されます。■あにき
寿司屋の隠語。これは先に使う材料のことをいいます。 反対にあとから使う食材を「おとうと」といいます。
■あらじこみ
ある程度材料を使える状態まで処理しておくこと。 さらに材料の仕込みが行われたのを「なかじこみ」といいます。
■オドリ
 車えびのにぎりで活きたまま握ったもの。車えびが踊るように動くことから。
車えびのにぎりで活きたまま握ったもの。車えびが踊るように動くことから。■かっぱ
 きゅうりのこと。きゅうりの切り口がかっぱの頭のさらに似ているとか、かっぱの好物という所からきています。
きゅうりのこと。きゅうりの切り口がかっぱの頭のさらに似ているとか、かっぱの好物という所からきています。■がり
しょうがのこと。噛んだときの音が「ガリガリ」という歯ごたえの音からきています。 がりには魚の生臭みを取ったりする口直しの役目のほかに、殺菌作用の役目もあります。
■ギョク(玉)
玉子焼きのこと。漢字の玉の音読みからきています。
■クサ
海苔のこと。海苔を「海草」という所からこう呼ばれています。
■軍艦巻き
 しゃりとねたを海苔でくるんだ寿司のこと。いくら、うに、小柱などがあります。
しゃりとねたを海苔でくるんだ寿司のこと。いくら、うに、小柱などがあります。■げそ
イカの足のこと。脱いだ履物を「下足(げそく)」と呼んだことから。
■げた
寿司をのせるもの。横から見ると下駄のように見えることから。
■しゃり
寿司飯のこと。仏舎利(お釈迦様の遺骨)からきています。地域によっては「赤シャリ」と呼ばれるしゃりもあります。
これは酒粕を数年熟成させると酒粕の色が赤く変化し、この貯蔵酢と米を主原料にして作られた酢を「赤酢」といい、 それを使ったしゃりをいいます
■たち
昔は寿司屋は店のほかに屋台という形の寿司屋もありました。昔は座って握っていました。 終戦後、衛生上の都合から店内で握られるようになり、店内で立って握ったことから「たち」と呼ばれるようになりました。
■タネ、ネタ
寿司の材料のこと。
■づけ
まぐろを醤油だれに漬け込んだもの。「漬ける」という所からきています。 昔は魚を長く保存されるために漬け込む技術が使われました。
■つけ場
寿司屋の調理場のこと。寿司を作ることや出すことを「つける」と呼ばれていたという説と、 昔の寿司が魚の漬け込みだったことからこう呼ばれる説もあります。
■つめ(煮つめ)
 穴子を煮た汁を煮つめて作った甘いたれのこと。穴子やしゃこなどに塗ります。
穴子を煮た汁を煮つめて作った甘いたれのこと。穴子やしゃこなどに塗ります。■鉄火
マグロの赤身を中心に巻いたのり巻きのこと。昔、賭博場を鉄火場と呼んでいて、 博打を打ちながら食べやすいように作ったのり巻きからきています。
■てんち
材料の頭と尾の部分。
■とろ
マグロの腹身のこと。脂肪が多く「とろっ」としたところから。
■どんしゃり
寿司飯ではない普通のご飯のこと。
■なみだ
 わさびのこと。ききすぎると涙が出てくるということからきています。
わさびのこと。ききすぎると涙が出てくるということからきています。■煮きり
醤油に酒などを加えて煮きり、醤油の臭みを消したもの。
■光もの
寿司だねのなかで皮の光った魚。こはだ、あじ、さんま、いわしなどの魚のことを言います。
■むらさき
お醤油のこと。醤油の色からきています。
■ヤマ
笹のこと。山で取れることからこのように呼ばれています。